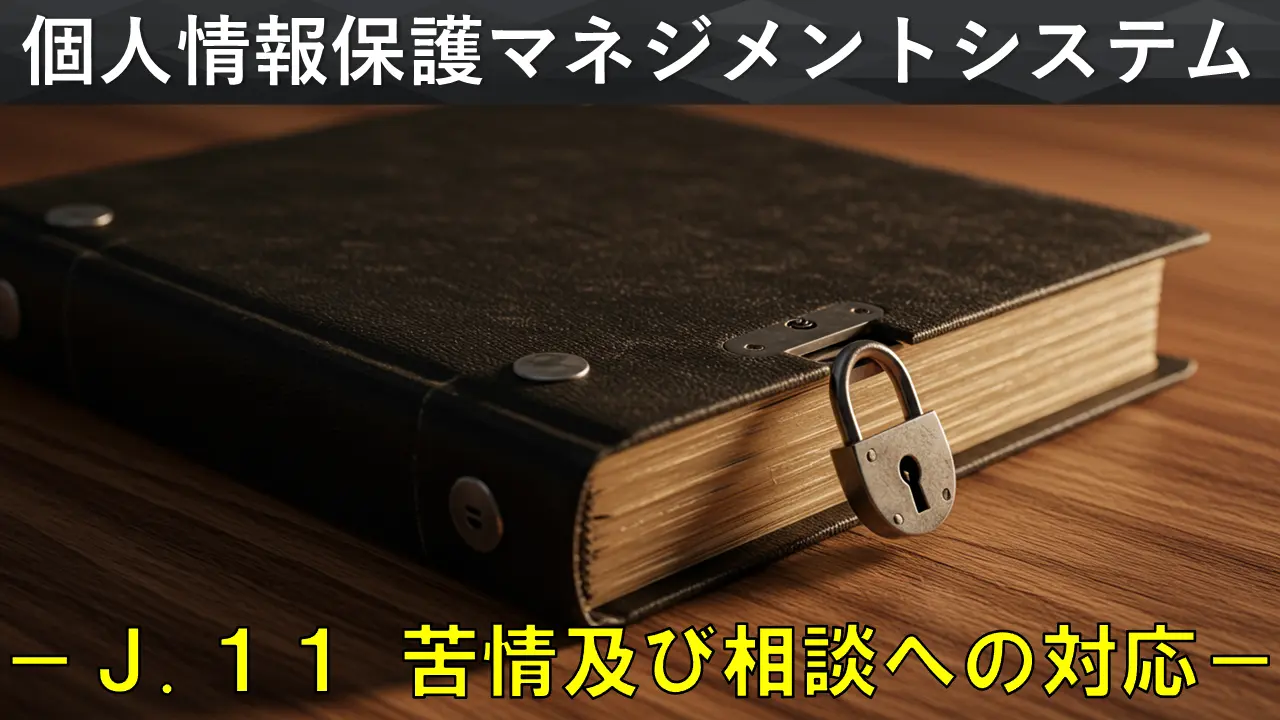
個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針を徹底解説 -「J.11 苦情及び相談への対応」編-
最終更新日:2025/11/13
こんにちは。
このシリーズでは、新しくなったプライバシーマーク(Pマーク)の「個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」について、セクションごとに紹介させていただいています。
前回は、「J.10 個人情報に関する本人の権利」について紹介しました。
個人情報の「持ち主」である本人が持つ、
「利用目的の通知(J.10.4)」
「開示(J.10.5)」
「訂正等(J.10.6)」
「利用停止等(J.10.7)」
といった、法律や指針で定められた「公式な権利」の行使に対して、事業者がどう応えるべきか、その「手順(J.10.2)」や「周知(J.10.3)」を含めた、非常に重要なルールでしたね。
さて、J.10で紹介したのは、本人からの「権利行使」という、どちらかというと公式で、法的な「請求」への対応でした。
しかし、日々の業務においては、そこまで堅苦しくない、
「私の情報、ちゃんと管理されてますか?」
「この前送られてきたメールマガジンは、どういう根拠で送っているのですか?」
「個人情報の取り扱いについて、ちょっと聞きたいことがあるのですが…」
といった、日常的な「苦情」や、漠然とした不安から来る「相談」も寄せられるはずです。
今回は、指針の11番目のセクションであり、要求事項としては最後となる「J.11 苦情及び相談への対応」について、じっくりと中身を紹介していきたいと思います。
このJ.11は、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の運用において、本人(お客様、従業者など)との、最も直接的で、最も日常的な「接点(窓口)」を、いかに誠実に運営するかを定めたルールです。
J.10が「法的な権利」の窓口だとすれば、J.11は「信頼関係」を築くための窓口と言えるかもしれません。
「J.11 苦情及び相談への対応」セクションは、項目としては「J.11.1 苦情及び相談への対応」の一つだけです。
しかし、この一つの項目には、個人情報保護に対する企業の「姿勢」そのものが問われる、非常に重い意味が込められています。
J.1からJ.10までで、どれだけ立派な「家(PMS)」を建て、どれだけ厳格な「ルール(J.8, J.9)」を定めても、このJ.11の「窓口」の対応がずさんであれば、本人(お客様)からの信頼は、一瞬で失われてしまうからです。
J.11.1 苦情及び相談への対応

この項目では、事業者が、
「個人情報の取扱い」及び「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」に関して、
本人からの「苦情」及び「相談」を受け付けて、
「適切」かつ「迅速」に対応することを求めています。
対象となるのは、「個人情報の“取り扱い”そのもの」(例:「目的外利用された」「漏えいした」)に対する苦情だけでなく、
「“PMSそのもの”」(例:「御社の個人情報保護方針が分かりにくい」「開示請求の手続きが複雑すぎる」「そもそも、ちゃんと管理体制があるのか?」)
といった、仕組み全体に関する苦情や相談も、広く受け止める必要がある、という点がポイントです。
指針では、この要求に応えるために、事業者が実施すべきことを、4つのステップ(No.1~No.4)で示しています。
1. 手順の文書化
まず、指針のNo.1では、
「本人からの苦情及び相談を受け付けて、適切かつ迅速な対応を行う手順」
を、「内部規程として文書化する」
ことを求めています。
「手順を文書化する」と聞くと、J.10.2(開示等の請求等に応じる手続)と似ているな、と思われるかもしれません。
J.10.2が「本人確認」や「手数料」など、公式な「請求」に対応するための、どちらかというと厳格な「手続き」を定めたのに対し、
J.11.1の「手順」は、より間口が広く、日常的な「苦情」や「相談」を、
「どのように受け付け」
「受け付けた後、社内の誰に引き継ぎ」
「事実関係をどう調査し」
「いつまでに、どのような形で本人に回答し」
「その対応をどう記録するか」
といった、一連の「社内業務フロー」を定めることを指します。
ここで重要なのが、「適切」かつ「迅速」というキーワードです。
「適切」とは
本人に寄り添い、誠実に対応することです。
面倒くさそうな態度をとったり、部署間で「たらい回し」にしたりするようなことは、最も避けなければならない対応です。
「迅速」とは
いたずらに本人を待たせないことです。
もちろん、調査に時間がかかる場合もありますが、その場合でも、「まずは受け付けた旨を連絡する」「調査に〇日ほどかかる見込みです」といった、中間報告を入れる配慮が求められます。
社内で、回答までの「標準的な期間(目安)」を決めておくことも、「迅速」な対応のための有効な手順となります。
2. 体制の整備
次に、指針のNo.2では、
「適切かつ迅速な対応を行うための体制を整備する」
ことを求めています。
「手順(ルールブック)」を作っただけでは、窓口は機能しません。
添付資料(Wordファイル)の解説にもある通り、「体制の整備」とは、具体的には、
窓口の設置
(例:専用の電話番号、メールアドレス、Webフォームの設置)
要員の配置
(その窓口に、実際に対応する「人」を配置すること)
手順の確立
(No.1で文書化した手順を、担当者が実行できるように周知・徹底すること)
といった、物理的・人的な準備を指します。
特に重要なのが「要員(担当者)」です。
添付資料(Wordファイル)の解説では、「対応要員の教育訓練を行うなどの工夫が必要」とされています。
なぜなら、J.11の窓口は、J.10の「請求」窓口とは異なり、時には本人の強い「怒り(苦情)」や、漠然とした「不安(相談)」を、真正面から受け止める、非常にデリケートな役割を担うからです。
担当者には、個人情報保護の「専門知識(J.4.2 力量)」や「保護意識(J.4.3 認識)」はもちろんのこと、本人の話を傾聴し、冷静に、かつ共感を持って対応する「コミュニケーションスキル」も、強く求められるのです。
3. 申出先の周知
次に、指針のNo.3では、
「苦情及び相談の申出先」
を、「本人の知り得る状態に置く」
ことを求めています。
これは、J.10.3(保有個人データに関する事項の周知など)の d) や e) で求められていたことと、全く同じ要求です。
「手順(No.1)」と「体制(No.2)」を整えても、その「窓口」の存在を本人(お客様)が知らなければ、意味がありません。
「本人の知り得る状態」とは、一般的には、自社のウェブサイトの「プライバシーポリシー」や「個人情報の取り扱いについて」のページに、
「個人情報に関する苦情・相談窓口」
として、専用の電話番号、メールアドレス、Webフォームへのリンクなどを、分かりやすく記載しておくことを指します。
(J.10.2で定めた「開示等の請求窓口」と、このJ.11.1の「苦情・相談窓口」は、結果として同じ窓口(例:「個人情報お問い合わせ窓口」)が兼ねるケースが多いですが、指針上は、異なる目的の窓口として、両方の役割を果たすことが求められています)
また、もし事業者が「認定個人情報保護団体」の対象事業者である場合は、
「当該団体の苦情解決の申出先も含む」
必要があります。
これは、本人にとって、「何かあった時に、事業者(当事者)だけでなく、中立的な第三者機関にも相談できる」という、大きな「安心感」につながります。
4. 苦情及び相談への対応の実施
そして、指針のNo.4は、
「苦情及び相談への対応を実施すること」
と、シンプルに「実行(Do)」を求めています。
No.1~No.3で整備した「手順」「体制」「周知」を、絵に描いた餅にせず、実際に寄せられた「声」に対して、誠実に対応(運用)しなさい、ということです。
そして、この「対応」には、必ず「記録」が伴います。
J.4.5.5(記録の管理)の f) で、「苦情及び相談への対応記録」を作成・管理することが求められていました。
「いつ、誰から、どのような苦情(相談)があり、どのように調査し、いつ、誰が、どのような回答をしたか」
という一連の対応履歴を、きちんと「記録」として残すことが、適切に対応した「証拠(エビデンス)」になると同時に、この後で紹介する、最も重要な「改善」活動のための、貴重な「財産」となります。
5. 苦情・相談の「改善」への活用(PDCAサイクルへの連携)
さて、J.11.1の要求事項は、表面的には「対応を実施すること(No.4)」で終わりです。
しかし、Pマーク(PMS)の真価は、ここから始まります。
寄せられた「苦情」や「相談」といった「本人の生の声」は、単に対応して「クローズ」すれば終わり、という「コスト」ではありません。
これこそが、J.7.2「継続的改善」で紹介した、PMSをより良くしていくための、最も貴重な「改善の機会(宝の山)」なのです。
このJ.11の活動は、PDCAサイクルの他のプロセスと、以下のように密接に連携しています。
C(Check)へのインプット
J.11で受け付けた「苦情及び相談への対応記録」は、J.6「パフォーマンス評価」における、最も重要な「インプット(評価材料)」の一つとなります。
特に、J.6.3「マネジメントレビュー」において、トップマネジメントは、No.3 d)「利害関係者からのフィードバック」として、これらの「苦情・相談」の傾向(例:「今月は〇〇に関する相談が急増している」)や、重大な苦情の内容について、必ず報告を受け、レビュー(評価)する必要があります。
A(Act)へのインプット
そして、その「C(Check)」の結果、トップマネジメントや個人情報保護管理者が「これは問題だ」と判断すれば、J.7「改善」のアクションにつながります。
・もし、苦情の内容が、明らかに「ルール違反(不適合)」であった場合(例:「同意なく目的外利用された」など)
→ J.7.1「不適合及び是正処置」のプロセスに乗り、直ちに「修正(対処)」するとともに、「原因」を究明し、「再発防止策(是正処置)」を講じる必要があります。
・もし、不適合とまでは言えなくても、「ルールが分かりにくい」「手続きが面倒だ」といった「改善の機会」であった場合
→ J.7.2「継続的改善」の活動として、次回のPMSの見直し(次のP)に反映させることになります。
このように、J.11の「苦情・相談窓口」は、単なる「ガス抜き」の窓口ではなく、PMS全体のPDCAサイクルを回すための、重要な「起点(インプット)」としての役割を担っているのです。
まとめ
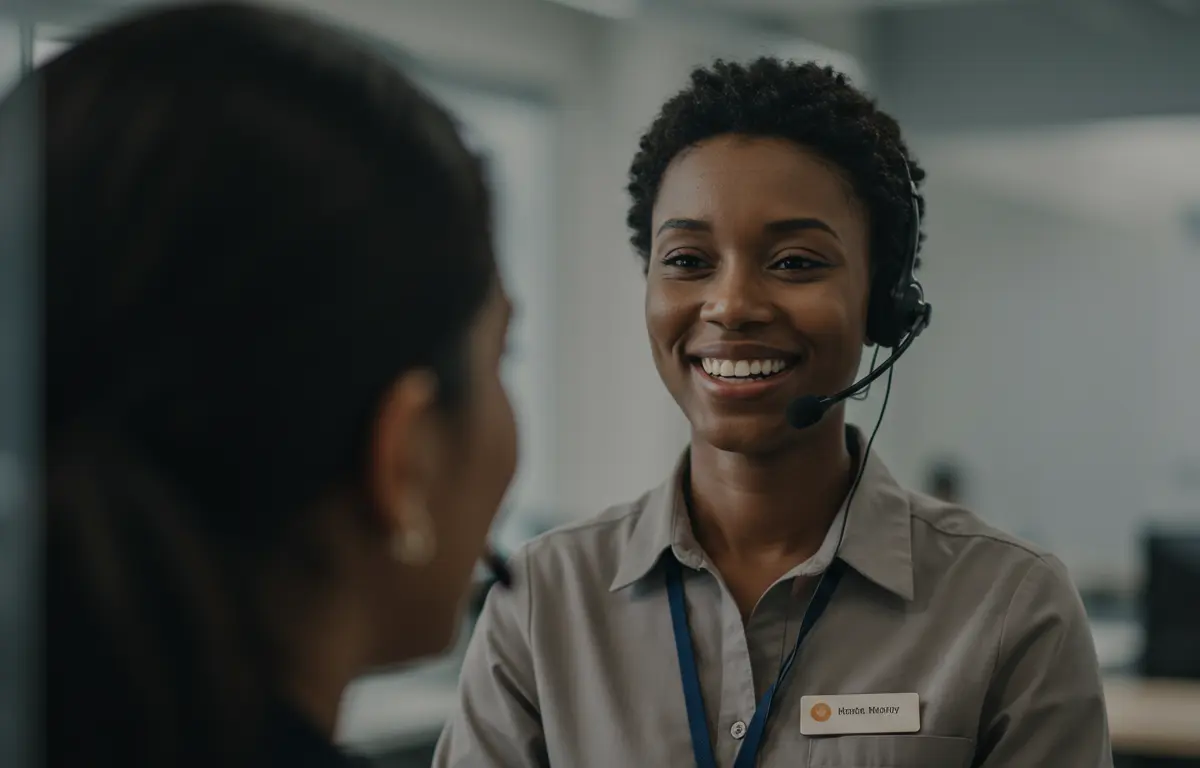
いかがでしたでしょうか。
今回は、新しいPマーク構築・運用指針の、最後の要求事項である「J.11 苦情及び相談への対応」について、その概要を紹介させていただきました。
「苦情」と聞くと、ネガティブなイメージを持つかもしれません。
しかし、PMSの運用において、本人(お客様)からの「声(苦情・相談)」は、J.6.2の「内部監査」やJ.6.1の「日常点検」では見つけられなかった、組織の「弱点」や「改善のヒント」を、外部の視点から教えてくれる、非常に貴重な情報源です。
このJ.11の窓口を、「クレーム処理係」としてではなく、本人との「信頼構築の接点」であり、PMSを「継続的改善」させるための「センサー」として、前向きに整備・運用すること。
それこそが、指針の最後を締めくくるJ.11が、私たち事業者に求めている「姿勢」なのだと思います。
さて、J.1「組織の状況(前提)」から始まり、J.2「リーダーシップ(体制)」、J.3「計画(P)」、J.4「支援(Dの基盤)」、J.5「運用(D)」、J.6「パフォーマンス評価(C)」、J.7「改善(A)」という、PMSの「PDCAサイクル(家の建て方)」を紹介しました。
そして、J.8「取得、利用及び提供に関する原則」、J.9「適正管理」、J.10「個人情報に関する本人の権利」、そして今回のJ.11「苦情及び相談への対応」という、PMSの中で取り扱う「具体的なルール(家の財産の扱い方)」を紹介しました。
この「J.1」から「J.11」までの全ての要求事項を、J.7.2「継続的改善」の精神で、毎年、あるいは日々、ぐるぐると回し続けること。
それが、プライバシーマーク(PMS)の「構築・運用」そのものであり、決して終わりのない活動(旅)です。
この紹介を通じて、皆さんの会社のPMSを今一度見直し、お客様や社会から「信頼」され続ける企業であるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。



