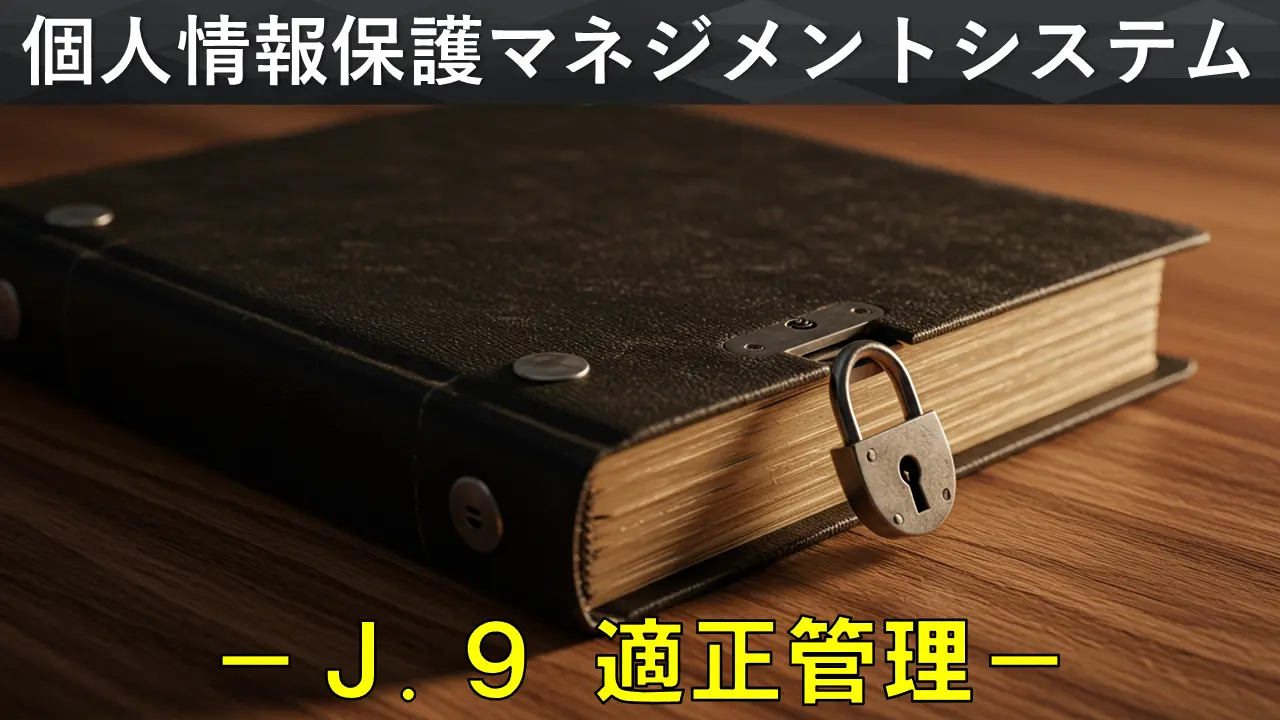
個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針を徹底解説 -「J.9 適正管理」編-
最終更新日:2025/11/13
こんにちは。
ここでは、新しくなったプライバシーマーク(Pマーク)の「個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」について、セクションごとに紹介させていただいています。
前回は、指針の中でも最もボリュームがあり、実務の「心臓部」とも言える「J.8 取得、利用及び提供に関する原則」について紹介しました。
個人情報の「入り口(取得)」、「内部での取り扱い(利用)」、そして「出口(提供)」という一連の流れ(ライフサイクル)における、厳格なルールでしたね。
特に、Pマーク独自の上乗せルールである「書面による同意(J.8.5)」や、近年ますます複雑化する「外国にある第三者への提供(J.8.8.1)」、「個人関連情報(J.8.8.4)」など、日々の業務で意識すべき重要なポイントがたくさんありました。
さて、J.1~J.7で「家(PMSの枠組み)」を建て、J.8でその家の大切な「財産(個人情報)」を「どう動かすか(取得・利用・提供)」という、非常に重要な「取り扱いルール」を学びました。
しかし、ルールを決めただけでは、「財産」は守れません。
その財産を、泥棒や火事、あるいは単なる紛失から守るための、「金庫」や「鍵」、「防犯システム」、「警備員」が必要ですよね。
今回は、指針の9つ目のセクションである「J.9 適正管理」について、じっくりと中身を紹介していきたいと思います。
この「J.9 適正管理」は、J.8で定めたルールで取り扱われる個人情報を、「いかにして正しく、かつ安全に管理し続けるか」という、「守り」の核心部分を定めたセクションです。
家づくりで言えば、まさに「防犯・防災設計」と「警備体制の構築」にあたる部分です。
「J.9 適正管理」セクションは、個人データを「正確」な状態に保ち、「安全」に管理し、それを取り扱う「人(従業者)」と「外部のパートナー(委託先)」を、適切に「監督」するための、4つの重要な項目で構成されています。
J.9.1 正確性の確保
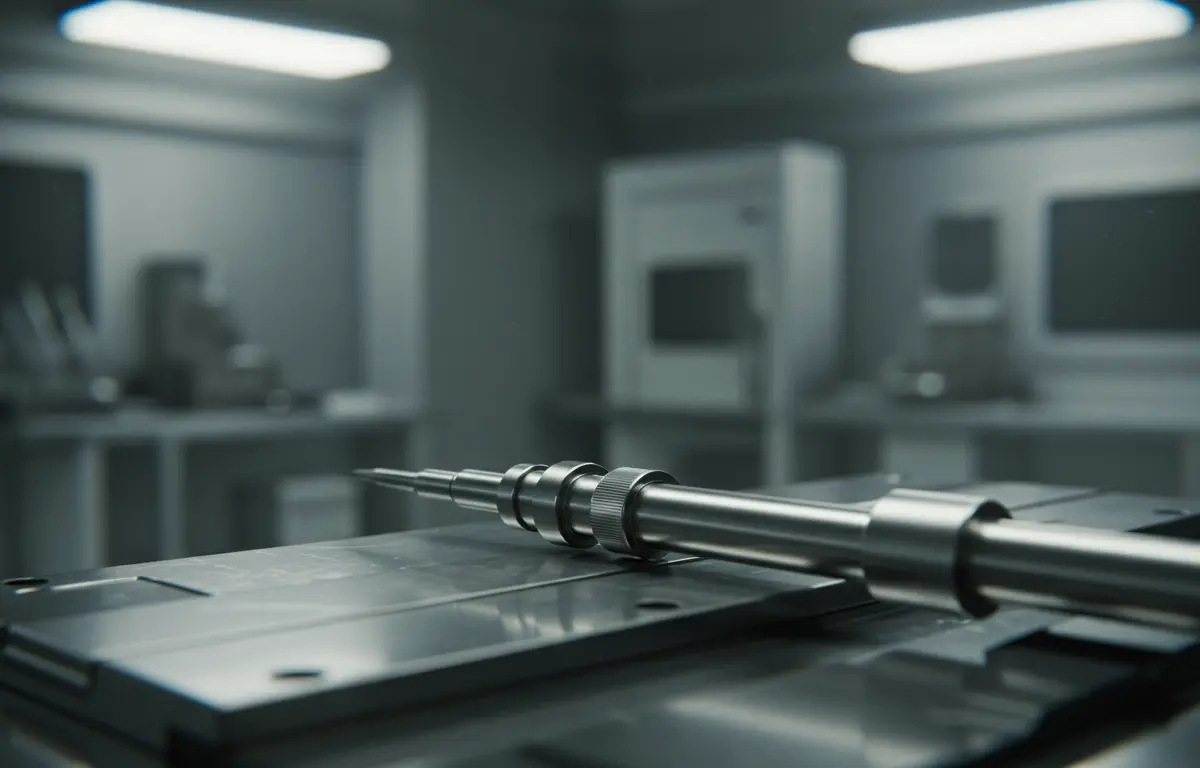
まず、最初の項目は「正確性の確保」です。
これは、「データ内容の正確性の確保」とも呼ばれ、安全に守る(セキュリティ)以前の大前提として、「そもそも、管理しているデータの中身が、古かったり、間違っていたりしてはいけない」というルールです。
利用目的の達成に必要な範囲内で、「正確」かつ「最新」に
指針では、「利用目的の達成に必要な範囲内において」、個人データを「正確、かつ、最新の状態で管理する」ことを求めています。
ここでのポイントは、「利用目的の達成に必要な範囲内において」という部分です。
例えば、顧客に「商品を発送する」という利用目的がある場合、顧客が引っ越したにもかかわらず、古い住所データを使い続ければ、商品は届かず、利用目的は達成できません。
それどころか、全く関係のない第三者(新しい入居者)に個人情報(氏名や購入履歴)が知られてしまうという、重大な情報漏えい事故につながる可能性もあります。
このように、利用目的にとって「正確性」「最新性」が必要不可欠な場合は、事業者はデータを常に正しい状態に保つ努力(例:本人に住所変更の手続きを促す、定期的にデータのクレンジングを行うなど)をしなければなりません。
一方で、利用目的の達成に影響しない情報(例:過去の統計データとして利用するだけで、本人への連絡には使わない情報)まで、常に最新化する必要はない、とも解釈できます。
自社の「利用目的」に照らし合わせて、どこまでの「正確性・最新性」を担保すべきか、その手順を確立し、実施することが求められます。
利用する必要がなくなった場合の「消去」
そして、J.9.1には、もう一つ非常に重要な要求事項があります。
「個人データの管理(利用する必要がなくなった場合の消去を含む。)は、定めた手順に基づいて適切に行うこと」。
これは、J.3.1.1の「個人情報管理台帳」で定めた「利用期限」や「保管期限」とも密接に関連します。
個人情報は、その利用目的が達成され、「利用する必要がなくなった」場合には、「遅滞なく消去しなければならない」のが大原則です。
(※添付資料(Wordファイル)の解説にもある通り、税法や労働法など、他の「法令により保存期間が定められている場合」は、もちろんその法令が優先されます。その場合も、「なぜ保管し続けるのか」の根拠が明確になります)
データを不必要に長く持ち続けることは、それ自体が「目的外利用」につながるリスクや、万が一の漏えい時の被害を拡大させるリスク(=リスクの「溜め込み」)になります。
「いつまで利用し」「いつ消去するのか」という、個人情報の「出口戦略」までを、きちんと手順化しておくことが、「適正管理」の第一歩なのです。
J.9.2 安全管理措置

J.9セクションの中核であり、「守り」のルールそのものと言えるのが、この「J.9.2 安全管理措置」です。
J.8で決めたルールで個人情報を取り扱う際に、その情報が「漏えい、滅失又は毀損」(まとめて「漏えい等」と呼ばれます)することを防止するために、必要な対策を講じなさい、という要求です。
リスクアセスメントとの連動
では、どのような対策(措置)を講じればよいのでしょうか。
指針は、「取り扱う個人情報の個人情報保護リスクに応じて」、また「法令に基づき」、必要かつ適切な措置を講じること、と定めています。
「リスクに応じて」という点が、非常に重要です。
これは、J.3.1.3で実施した「個人情報保護リスクアセスメント」の結果と、完全に連動することを意味します。
アセスメントで「うちの会社は、ここが危ない(リスクが高い)」と特定された部分には、手厚い措置を講じ、逆にリスクが低いと評価された部分は、過剰にならない(費用対効果も考慮した)「適切な」措置を講じる。
このように、J.3の「計画(P)」と、J.9の「実行(D)」は、表裏一体の関係にあるのです。
4つの安全管理措置
では、具体的にどのような「措置」があるのでしょうか。
添付資料(Wordファイル)の解説にある通り、安全管理措置は、一般的に以下の「4つの観点」から、総合的に実施することが求められます。
1. 組織的安全管理措置
これは、「体制」や「ルール」の整備による守りです。
(例)
・個人情報保護管理者(J.2.3.2)の設置や、責任体制の明確化。
・個人情報の取り扱いに関する「内部規程(J.4.5.4)」の整備と運用。
・「個人情報管理台帳(J.3.1.1)」による、取り扱い状況の把握。
・事故や違反を発見した場合の「緊急事態対応体制(J.4.4.2)」の整備。
・日々の運用状況の「点検(J.6.1)」や「内部監査(J.6.2)」の実施。
2. 人的安全管理措置
これは、「人」に対する教育や監督による守りです。
(例)
・従業者に対する「教育(J.4.3)」の実施。
・入社時や、重要な情報を取り扱う部門への配置転換時に、「機密保持に関する誓約書」等を取得すること。
・従業者の「監督(J.9.3)」(後述します)。
・就業規則等に、PMS違反時の「罰則規定(J.4.5.4 o))」を定めること。
3. 物理的安全管理措置
これは、「モノ」や「場所」に対する、物理的な守りです。
(例)
・個人情報を取り扱う「区域」(オフィス、サーバルームなど)への入退室管理(例:ICカード、施錠)。
・個人情報が記載された「書類」や「媒体(USBメモリ、ノートPCなど)」の盗難・紛失防止策(例:施錠できるキャビネットでの保管、ワイヤーロックでの固定)。
・不要になった書類の「廃棄」(例:シュレッダー、溶解処理)。
・持ち運び時のルール(例:PCやUSBメモリの暗号化、許可制)。
4. 技術的安全管理措置
これは、「システム」や「ネットワーク」など、技術的な守りです。
(例)
・「アクセス制御」(例:IDとパスワードによる認証、担当業務に応じて必要な範囲だけアクセスできる権限設定)。
・「不正アクセス防止」(例:ファイアウォールの設置、ウイルス対策ソフトの導入と最新化)。
・「移送・送信時の保護」(例:通信経路の暗号化(SSL/TLS)、ファイル自体の暗号化)。
・「アクセスログ」の取得と監視。
Pマークの安全管理措置は、これら「組織的」「人的」「物理的」「技術的」の4つが、どれか一つに偏るのではなく、お互いを補完し合う形で、バランスよく実施されていることが重要です。
【2023年版準拠の改定点】クラウドサービスの利用(重要ポイント)
そして、添付資料(Wordファイル)の解説にもある通り、今回の指針改定(JIS Q 15001:2023準拠)に伴い、J.9.2(PDF P55 No.2)には、現代のビジネス環境を反映した、非常に重要な要求事項が追加されました。
それは、「外部サービスを利用する場合」に関する注意点です。
ここで言う外部サービスとは、特に「当該サービス提供事業者が当該個人データを取り扱わないことになっているサービス」を指します。
これは、どういうことでしょうか。
例えば、Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure のような「IaaS/PaaS型クラウドサービス」や、「レンタルサーバ」を借りて、自社でOSやアプリケーションを構築・管理する場合が、これにあたります。
この場合、クラウド事業者(AWSなど)は、あくまで「場所(インフラ)」を貸しているだけで、その上で顧客(自社)がどのような個人データを取り扱っているかには(契約上)関知しません。
そのため、これは「個人データの取り扱いを任せる」ことにはならず、この後で紹介する「委託(J.9.4)」には、該当しないと整理されることが一般的です。
しかし、だからといって「何もしなくて良い」わけではありません。
契約上は「委託」でなくても、「自社の重要な個人データを、他社の管理する設備(データセンター)に“預ける”」という事実は変わらないからです。
そこで、指針は、たとえ契約上「委託」にあたらなくても、「預ける側(事業者)の、自らの安全管理措置の一環」として、
「あらかじめサービス内容の把握、評価等を行ったうえで選定する」
ことを求めているのです。
(例)
・そのクラウドサービスは、十分なセキュリティ水準(例:ISMS認証など)を持っているか?。
・データセンターは、どこの国にあるのか?(J.8.8.1(外国への提供)のリスクはないか?)。
・障害発生時の対応体制はどうか?。
などを、利用開始前にきちんと「評価・選定」し、その上で利用しなさい、という、非常に現実的かつ重要な要求事項が追加されたのです。
J.9.3 従業者の監督

J.9.2の「人的安全管理措置」を、より具体的に実施するための項目が、「J.9.3 従業者の監督」です。
指針は、個人データを取り扱う「従業者」に対して、「必要かつ適切な監督」を行うことを求めています。
「従業者」の範囲
まず、対象となる「従業者」とは、J.2.1(リーダーシップ)の留意事項でも定義されていた通り、会社の指揮監督下で業務に従事する「全ての人」を指します。
正社員はもちろん、
・役員
・契約社員、嘱託社員
・パートタイマー、アルバイト
・派遣社員
なども、全て監督の対象となります。
特に、派遣社員については、派遣元(派遣会社)と派遣先(自社)の両方が監督責任を負うことになりますが、Pマーク事業者としては、自社の指揮命令下で働く以上、自社の従業員と「同等」の監督(教育やルールの遵守徹底)を行う必要があります。
「必要かつ適切な監督」とは
「監督」というと、監視カメラで見張るような、堅苦しいイメージがあるかもしれません。
しかし、ここでの「監督」とは、主に以下のような活動を指します。
・J.4.3に基づく「教育・訓練」を、対象者全員に確実に実施し、その内容を理解させること。
・J.4.5.4(o)の「罰則規定」を含む、個人情報の取り扱いに関する「内部規程」を周知し、遵守させること。
・「機密保持に関する誓約書」などを、入社時や(場合によっては)退職時に取得し、責任を自覚させること。
・J.6.1(監視・測定)などを通じて、日常業務の中でルールが守られているか(例:クリアデスク、PCの施錠、パスワードの使い回し禁止など)を、管理者が確認し、指導すること。
単に「人を信じない」ということではありません。
人がミスや勘違い(ヒューマンエラー)を起こしやすい生き物であることを前提に、「ルールを守る意識付け(教育・監督)」と、「万が一ミスをしても事故にならない仕組み(J.9.2の技術的・物理的措置)」の、両輪で守っていくことが「適切な監督」なのです。
J.9.4 委託先の監督
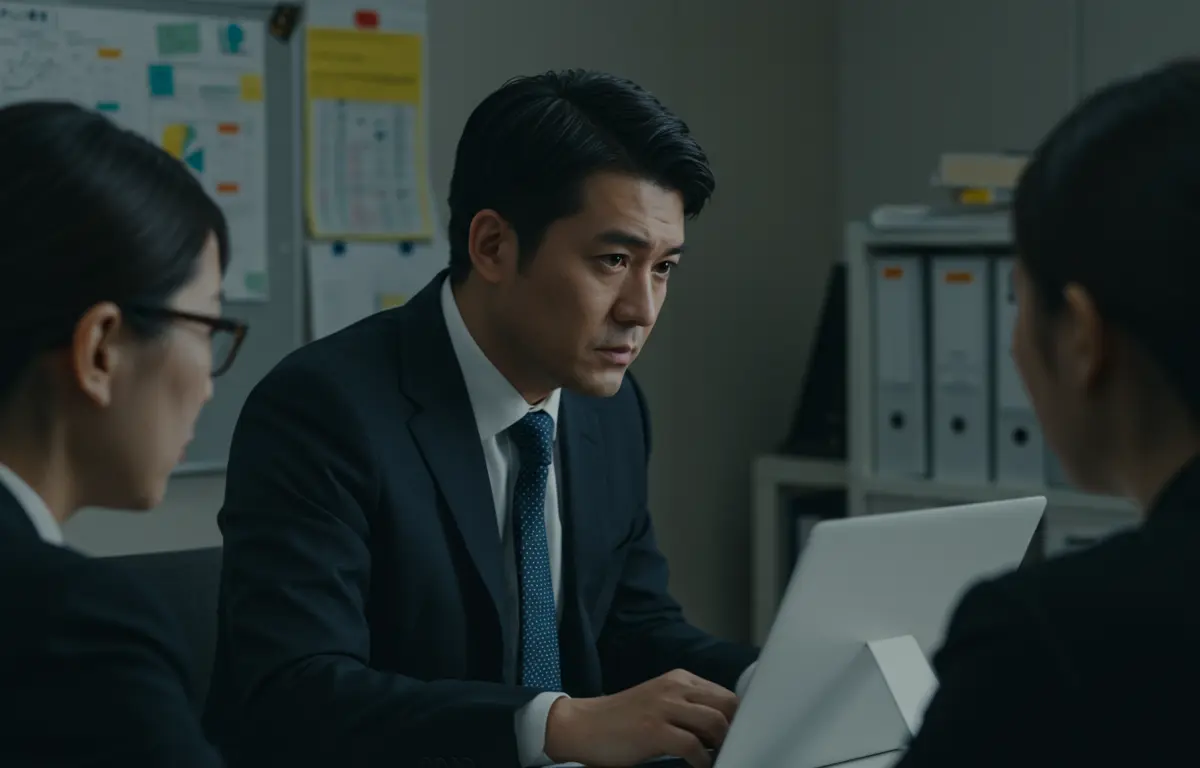
J.9の最後は、「J.9.4 委託先の監督」です。
J.9.3が「内部(従業者)」の監督だったのに対し、J.9.4は「外部(委託先)」の監督に関するルールです。
J.5.1のNo.4で「外部委託した業務も管理の対象とすること」と宣言されましたが、このJ.9.4では、その「具体的な管理方法」が定められています。
現代のビジネスでは、自社だけですべての業務を完結させることは稀です。
・給与計算業務を、社労士事務所に委託する。
・システムの開発・運用・保守を、ITベンダーに委託する。
・顧客データの入力作業を、データエントリー会社に委託する。
・ダイレクトメールの発送業務を、印刷・発送業者に委託する。
・個人情報が記載された書類の廃棄を、専門の廃棄物処理業者に委託する。
・従業員の名刺作成を、印刷会社に委託する。
これらはすべて、個人データの取り扱いを伴う「委託」にあたります。
添付資料(Wordファイル)の解説にもある通り、たとえ相手がグループ会社であっても、法人格が別であれば「委託」または「第三者提供(J.8.8)」として、適切に管理する必要があります。
この「委託先の監督」は、自社の管理が及ばない(と思いがちな)外部で、自社の名前で個人情報が取り扱われる、非常にリスクの高いポイントであり、Pマークの審査でも極めて厳しくチェックされる項目です。
指針では、委託先の監督を、大きく3つのプロセスに分けて要求しています。
1. 委託先の選定
まず、そもそも「誰に任せるか」の入り口が重要です。
指針は、「十分な個人データの保護水準を満たしている者」を選定するために、「委託先選定基準」を確立し、それに基づいて委託先を選定することを求めています。
「安ければ誰でもよい」は、絶対にダメだ、ということです。
「委託先選定基準」には、例えば、
・PマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの第三者認証を取得しているか。
・認証がなくても、自社(委託元)と同等以上の安全管理措置(J.9.2の4つの観点)が講じられているか。
・再委託(委託先が、さらに別の会社に任せること)の管理体制はどうか。
・事故発生時の報告・対応体制はどうか。
といった基準を設けます。
そして、この基準に基づき、候補となる委託先を「評価(アンケートやヒアリング、現地調査など)」し、基準を満たしていることを確認した上で、選定します。
これらの「基準書」や「評価(選定)した記録」は、適切に選定した証拠として、保管する必要があります。
2. 委託契約の締結
選定が完了したら、次は「契約」です。
指針は、「特定した利用目的の範囲内で」委託契約を締結することを求めています。
(例:「商品発送のため」に預かった情報を、委託先が勝手に「マーケティング分析」に使うことはできません)
さらに、その契約書(または覚書)には、「委託元(自社)が、委託先に対して監督できる」ように、以下の事項(a~h)を盛り込むことが求められています。
a) 委託者(自社)と受託者(委託先)の責任の明確化
b) 個人データの安全管理に関する事項(委託先に、J.9.2と同等の安全管理を義務付ける)
c) 再委託に関する事項(再委託は原則禁止か、許可制か。許可する場合の条件など)
d) 個人データの取扱状況に関する、委託者への報告の内容及び頻度
e) 契約内容が遵守されていることを、委託者が確認できる事項(例:監査権、立入検査権など)
f) 契約内容が遵守されなかった場合の措置(例:契約解除、損害賠償など)
g) 事件・事故が発生した場合の、報告・連絡に関する事項
h) 契約終了後の措置(預けた個人データの返却、または消去・廃棄)
これらの条項を盛り込んだ契約を締結し、その契約書を(個人データの保有期間中)保存しておく必要があります。
3. 委託先の監督
契約を結んだら、終わりではありません。
J.5.1の宣言通り、運用が始まった後も「管理対象」です。
指針は、「委託契約に基づき、委託先を適切に監督すること」を求めています。
具体的には、
「契約内容(特に、bの安全管理措置や、cの再委託の状況)が、きちんと遵守されているか」
を、定期的(例:年に1回)に、及び適宜に、確認(監督)します。
確認の方法としては、
・委託先に「個人情報取扱状況報告書」のようなセルフチェックシートを提出してもらう。
・Web会議や電話で、管理状況についてヒアリングする。
・(リスクが高いと判断した場合は)現地に赴いて、実際の管理状況を監査(現地調査)する。
といった方法が考えられます。
もし、この監督の過程で、契約違反や不十分な点が見つかった場合は、速やかに是正(改善)を求めることになります。
添付資料(Wordファイル)の解説にある通り、「全ての委託先をもれなく特定」し、これら「選定・契約・監督」の3ステップを、全ての委託先に対して(リスクの大きさに応じて濃淡はつけつつも)実施することが、J.9.4の要求事項なのです。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、新しいPマーク構築・運用指針の「J.9 適正管理」について、その概要を紹介させていただきました。
J.9は、個人情報を「適正に」管理し続けるための、「守り」の中核となるセクションでした。
J.9.1で、データの「中身」を「正確・最新」に保ち、不要になったら「消去」する。
J.9.2で、J.3のリスクアセスメントに基づき、「組織的・人的・物理的・技術的」の4つの観点から「安全管理措置」を講じる(クラウド利用時の注意点も含む)。
J.9.3で、内部の「従業者」を適切に「監督」する。
J.9.4で、外部の「委託先」を、「選定・契約・監督」の3ステップで厳格に「監督」する。
J.8で紹介した「取り扱い(取得・利用・提供)」のルールと、このJ.9で紹介した「管理(守り)」のルール。
この両方が揃って、初めて、事業者は個人情報を「適正に」取り扱っていると、胸を張って言えるようになるのです。



